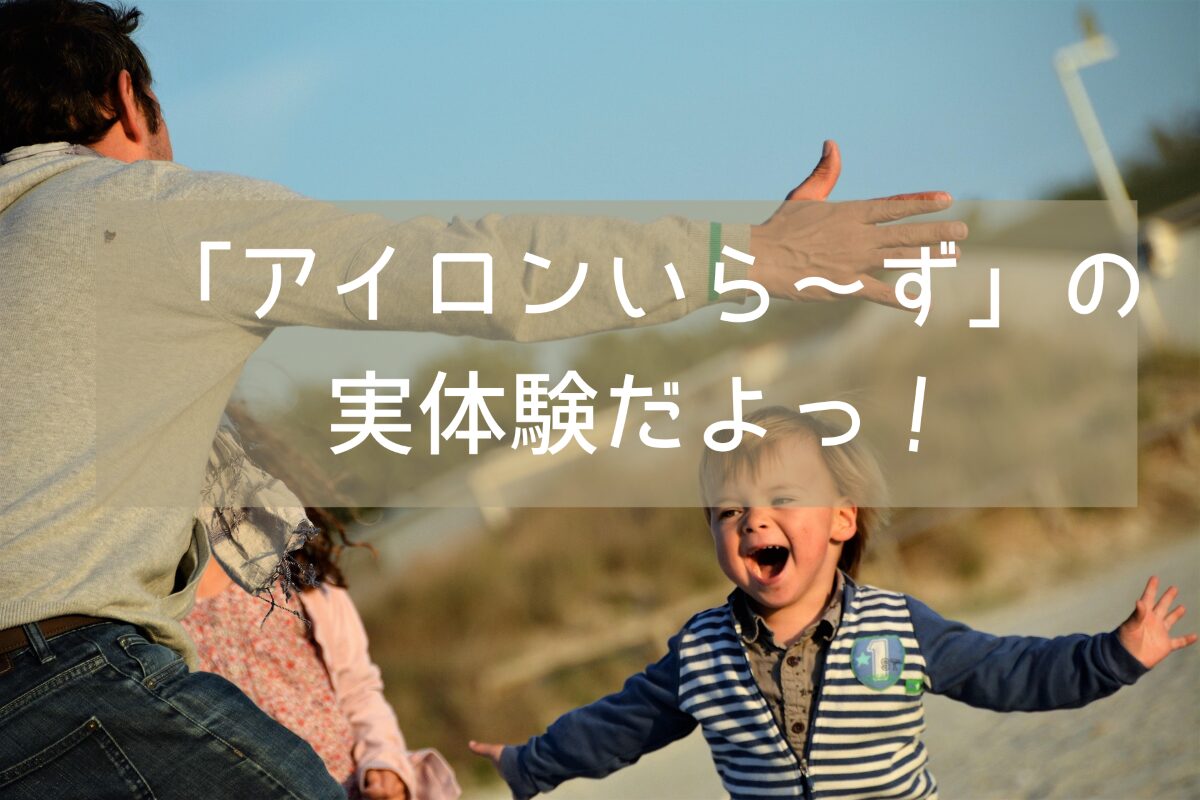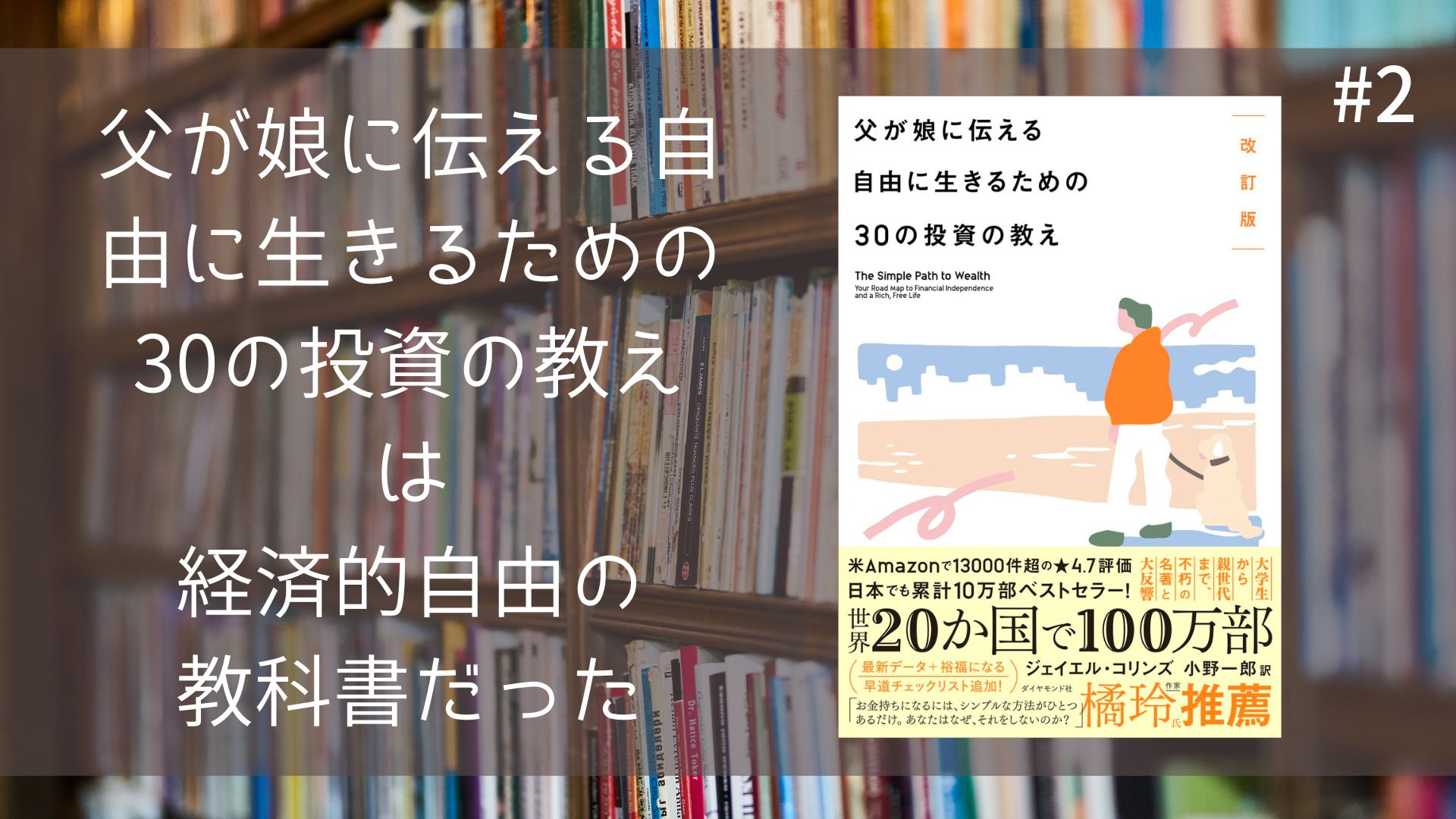『本を読む人はうまくいく』を読んだよ!
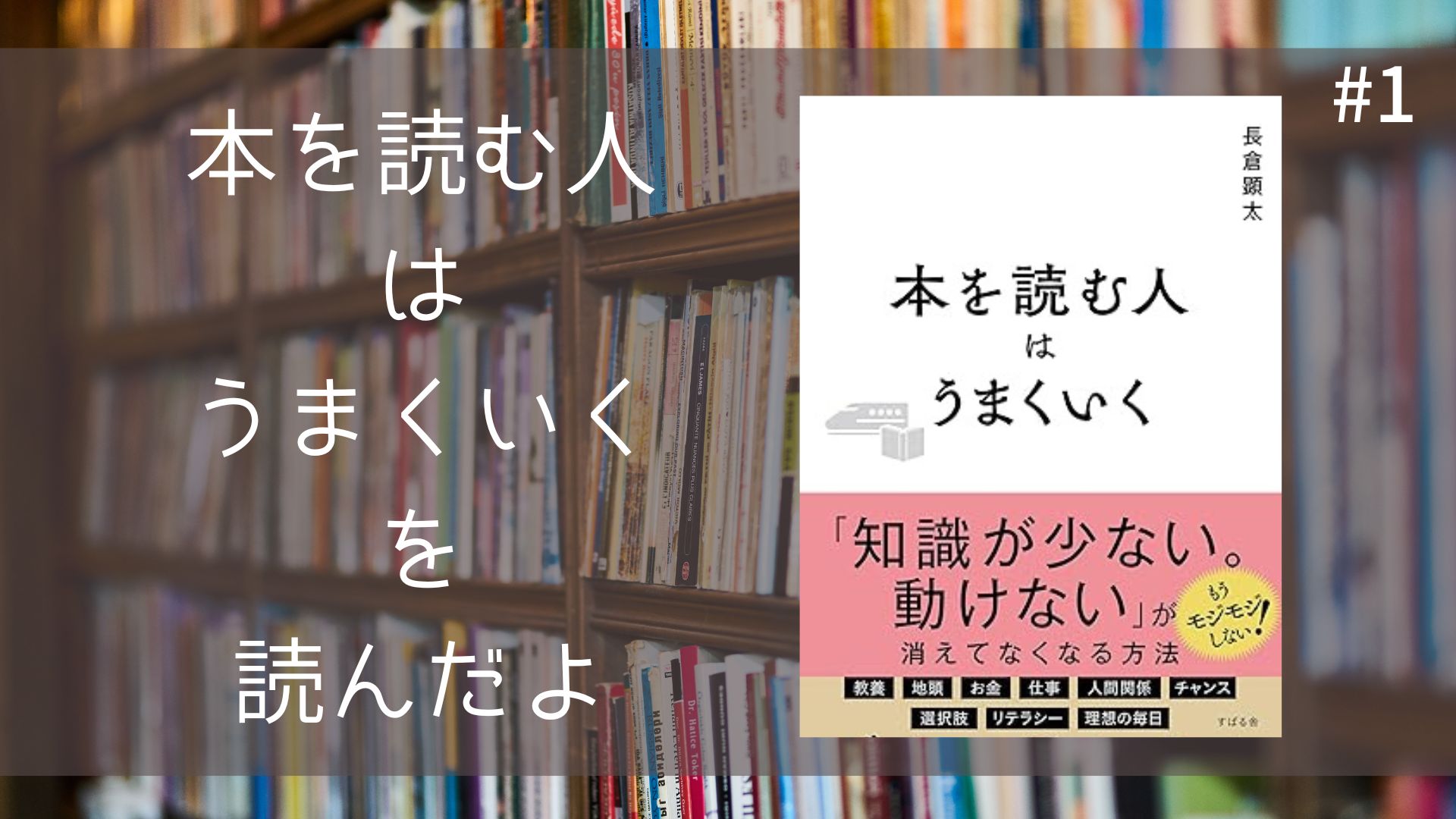
こんにちは。
建築と暮らしをテーマに発信しているあいにゃんです。今回は『暮らし』編です。
今回は、長倉顕太さんの著書『本を読む人はうまくいく』を読んで、印象に残った部分と、
そこから感じた「読書の力」についてまとめました。
本を読む意味を見失いかけている方や、最近SNSばかりで本を読んでいない方に、
ぜひ読んでほしい内容です。
1. 世界は情報でできている
この一文に、ハッとさせられました。
確かに、言語がなければ何も伝えられません。
「言葉」は単なる記号ではなく、情報そのもの。
情報を扱う力=言葉を扱う力が、私たちの世界の認知を支えています。
本でなければならない理由
著者は「本であることの意味」として、次の3つを挙げています。
①視野を広げる
②判断力が養われる
③リーダーシップが身につく
わたし自身、子どもに本を読んでもらいたい。
特に「読解力」という点では、Kindleなどの電子書籍よりも、
紙の本の方が“手触りや視覚など五感を使う”ことで、より深く理解できる気がしています。
認知できるものは全て言葉で説明できる
──この言葉も印象的でした。
確かに、言葉にできないものは、頭の中でも整理されません。
言語化することが、思考を磨く第一歩なのだと再確認しました。
読書がもたらす力
読書を通じて養われるのは、次の3つ。
視野が広がる 判断力が養われる リーダーシップが身につく
リーダーシップまで行き着くのは意外でしたが、
「多くの考え方を知り、他者を理解する力」こそが、
人を導く力になるのかもしれません。
本を読むことは追体験の宝庫
本を読むことで、他人の経験を“追体験”できます。
歴史上の人物の考え方、成功や失敗も、本を通じて疑似体験できる。
私はこれまで歴史本を避けてきましたが、この言葉と出会い、これからは「人物伝」などにも挑戦しようと思いました。
読書→行動 はワンセット
──この言葉は実に重い。行動が伴わない読書がいかに多いか…
この本を読んだ日、私はこのブログを始める決意をしました。
まずは“1本目”として、この記事を書いています
分野を広げて読む
著者は、以下のようにバランスの取れた読書を勧めています。
『ビジネス・経済』『科学・技術』『歴史・政治』『哲学・思想』『文学・小説』『自己啓発・心理学』『芸術・デザイン』『社会問題・時事』
今までの自分を振り返ると、ビジネス書ばかりでした。
これからは、1年間の読書をスプレッドシートで記録しながら、
分野のバランスを意識していこうと思います。
(Amazonで分野分けが少し難しいですが、メルカリの分類が参考になります)
SNS発信そして、、、著者に近づく
本の中で印象的だったのが、
「読書ノートは、好きな部分の引用と自分の気づきでいい」という部分。
私はこれをヒントに、ブログで気づきを発信することにしました。
そして、「著者に会いに行く」という言葉も行動のきっかけに。
長倉さんの講演会情報を調べ、
新刊キャンペーンと同時開催のトークイベント視聴に申し込みしました。まずは第一歩と思っています。このきっかけがないと、Amazonの作者紹介以上の行動に結び付きませんでした。
読んだ私の感想
『本を読む人はうまくいく』を読んで、「読書は自分の思考を磨き、行動を変えるものだ」と強く感じました。この本に触れたことで、「学びを発信しよう」という行動意欲が生まれ、実際にこのブログを書くきっかけにもなりました。
結果がどうであれ、読書は自分への投資。その投資を行動に変え、誰かの役に立てるなら、これほど幸せなことはありません。本はとても読みやすく、最後まで一気に読み切りました。読み終えた直後に、著者・長倉顕太さんの他の本をAmazonでまとめ買いしたほどです。
情報の洪水の中で、自分の軸を言葉で保ちたい人。
そして、学びを行動に変えたい人。
そんな人にこそ、この本を強くおすすめします。
今日も一冊、ページをめくることで人生が少し動く。
これからも、そんな読書を続けていきたいと思います。